|
|
はじめに
🛠️雨戸も外壁と同じように
定期的なメンテナンスが必要です
雨戸のサビや色褪せをそのままにしていませんか?
雨戸を塗り替えることで美観が戻るだけでなく
耐久性も格段に向上します
今回は町田市玉川学園で行った
雨戸塗装工をご紹介します
====================
⭐ 1. 塗装工事の重要性:なぜ雨戸を塗る必要があるの?
🌿雨戸の寿命を延ばすためです
雨戸は常に雨風や紫外線にさらされています
塗膜が劣化するとサビが発生しやすくなり腐食が進みます
サビが進行すると雨戸の開閉に支障が出たり
穴が開いたりする原因になります
町田市は住宅が密集している地域も多いため
近隣への配慮(景観維持)という点でも塗装は重要です
塗装は雨戸を保護し長く使えるようにするための
必須のメンテナンスです
🎨塗り替えのメリット
- 耐久性・防水性の向上
- サビの進行を食い止める
- 家の美観が向上する
- スムーズな開閉の維持
====================
⭐ 2. 町田市玉川学園での雨戸塗装工事の
流れとポイント【写真で解説】
1️⃣ 施工前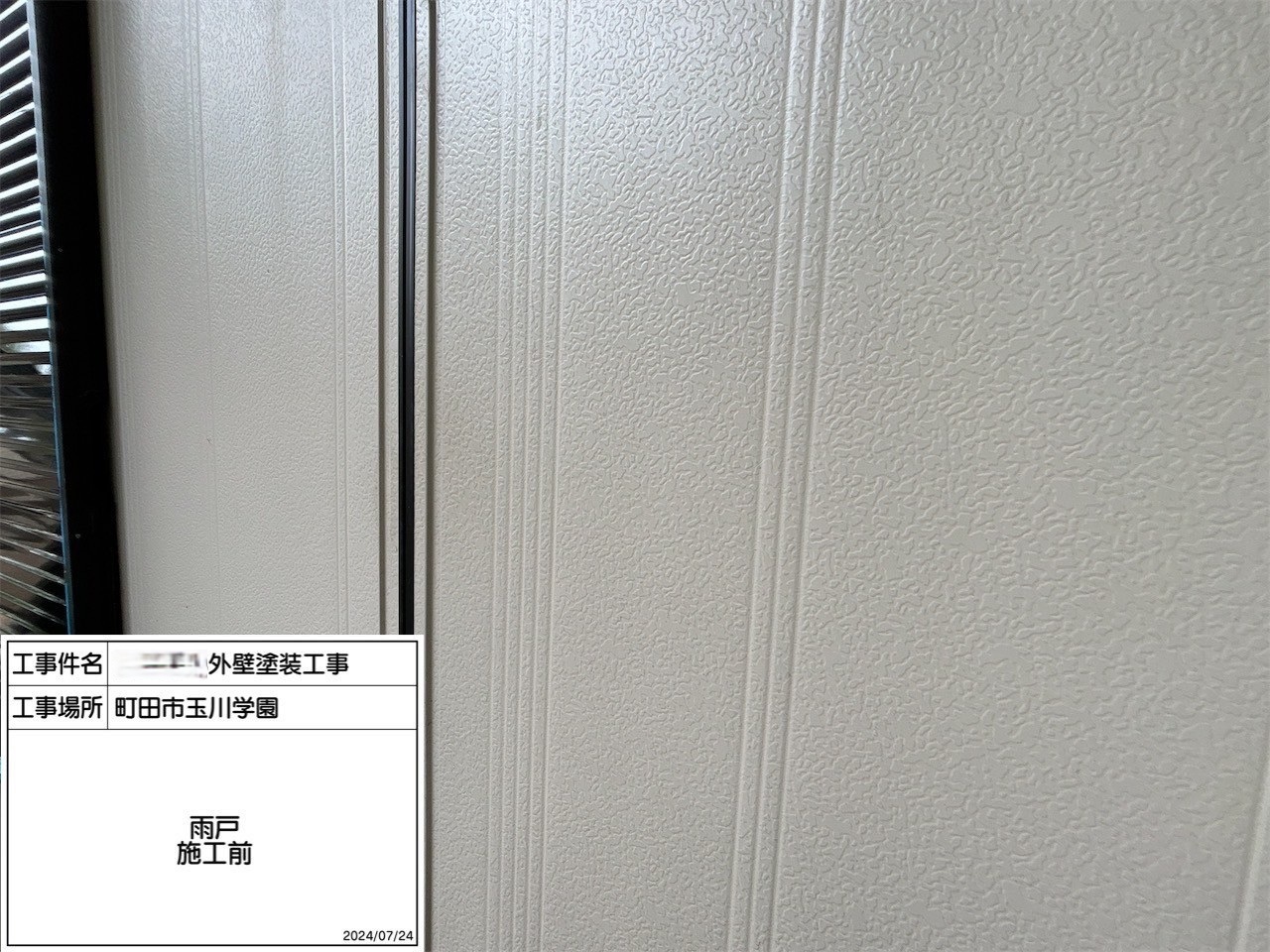
🔍現状を確認します
施工前の雨戸の状態です
まだ大きなサビは見られませんが塗膜のツヤがなくなり
全体的に色褪せが見られます
このまま放置するとサビが広がる可能性が
あるため適切なタイミングでの塗装工事です
お客様のご希望の色を伺い準備を進めます
2️⃣ ケレン(最も重要な下地処理)
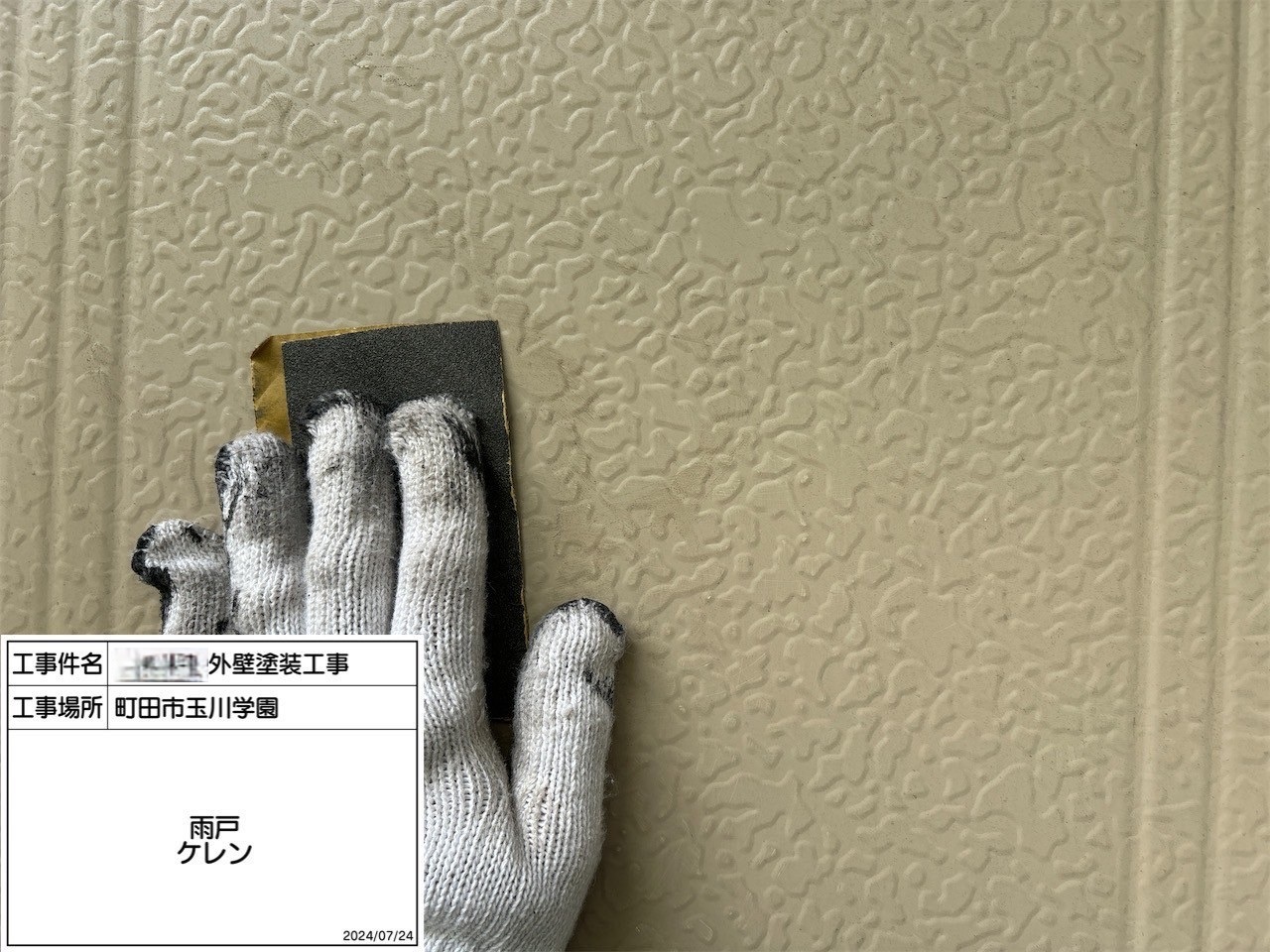
💪仕上がりを左右する大切な工程です
ケレンとはサンドペーパーやワイヤーブラシを使って
古い塗膜やサビを削り落とす作業です
雨戸塗装においてケレンは、本塗り以上に
重要な工程であり、耐久性を左右します
この下地処理を徹底することで
サビの再発を防ぎ塗料が剥がれるのを防ぎます
塗料の密着性を高めるための「目荒らし」も行います
丁寧にケレンを行うことで長持ちする美しい仕上がりになります
3️⃣ 下塗り(サビ止め)の実施
🛡️塗料を密着させる工程です
ケレンで下地を整えた後
サビの発生を抑えるための
下塗り(サビ止めプライマー)を塗布します
この下塗り材が、これから塗る中塗り・上塗り塗料を
雨戸にしっかりと密着させます
この工程を経ることで、塗膜の寿命が格段に長くなります
下塗りが完全に乾燥してから次の工程へ進みます
4️⃣ 中塗り(1回目の本塗装)
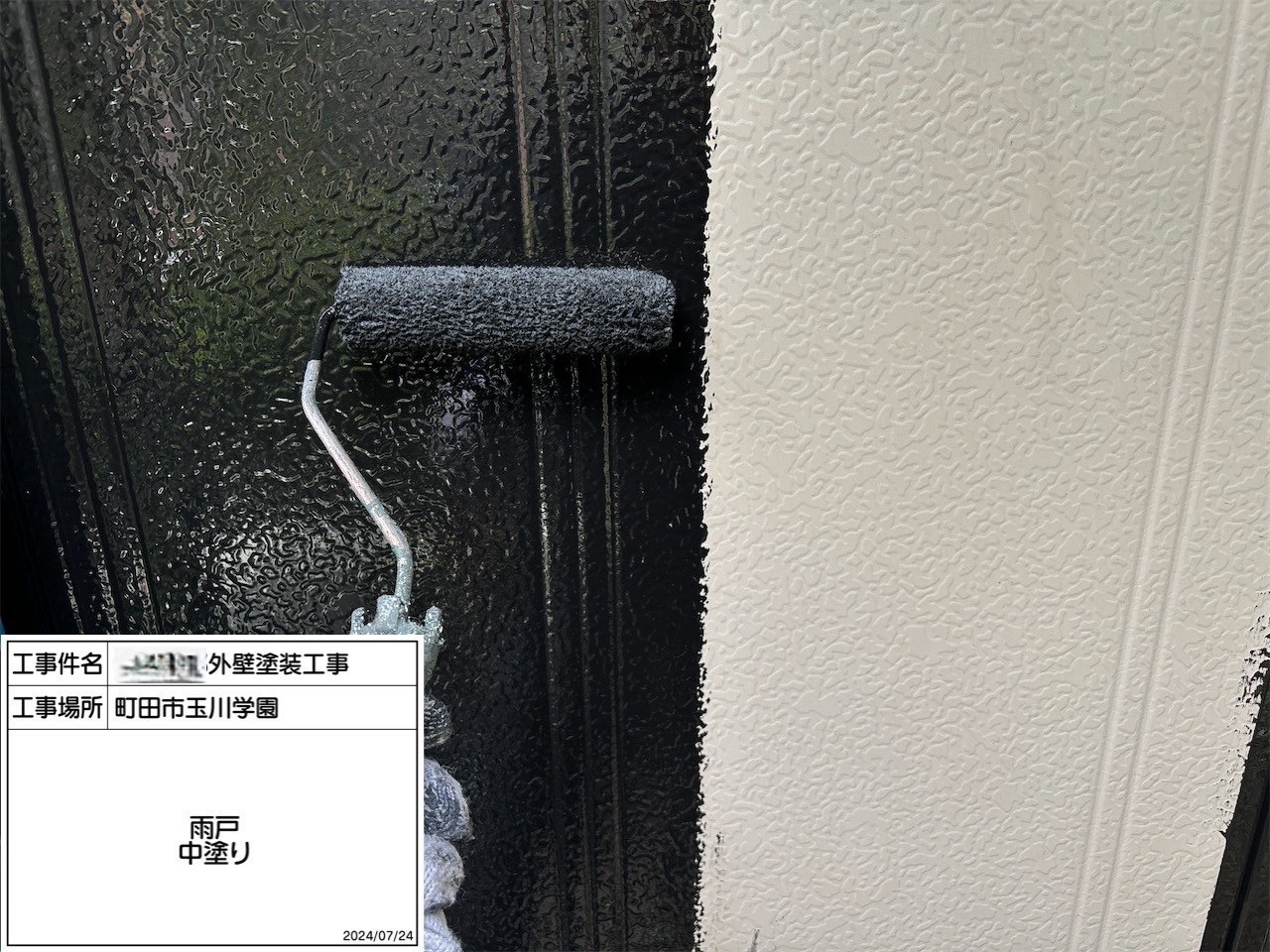
⚫︎塗料をたっぷりと塗布します
下塗りが終わったら1回目の本塗りに入ります
今回使用するのは耐久性の高い塗料の黒色です
中塗りは塗料の持つ性能を発揮させるために
必要な「膜厚」を確保する最初の工程です
ローラーを使ってムラなく均一に塗っていきます
複雑な形状の雨戸にもしっかりと塗料を浸透させます
5️⃣ 上塗り(仕上げ塗装)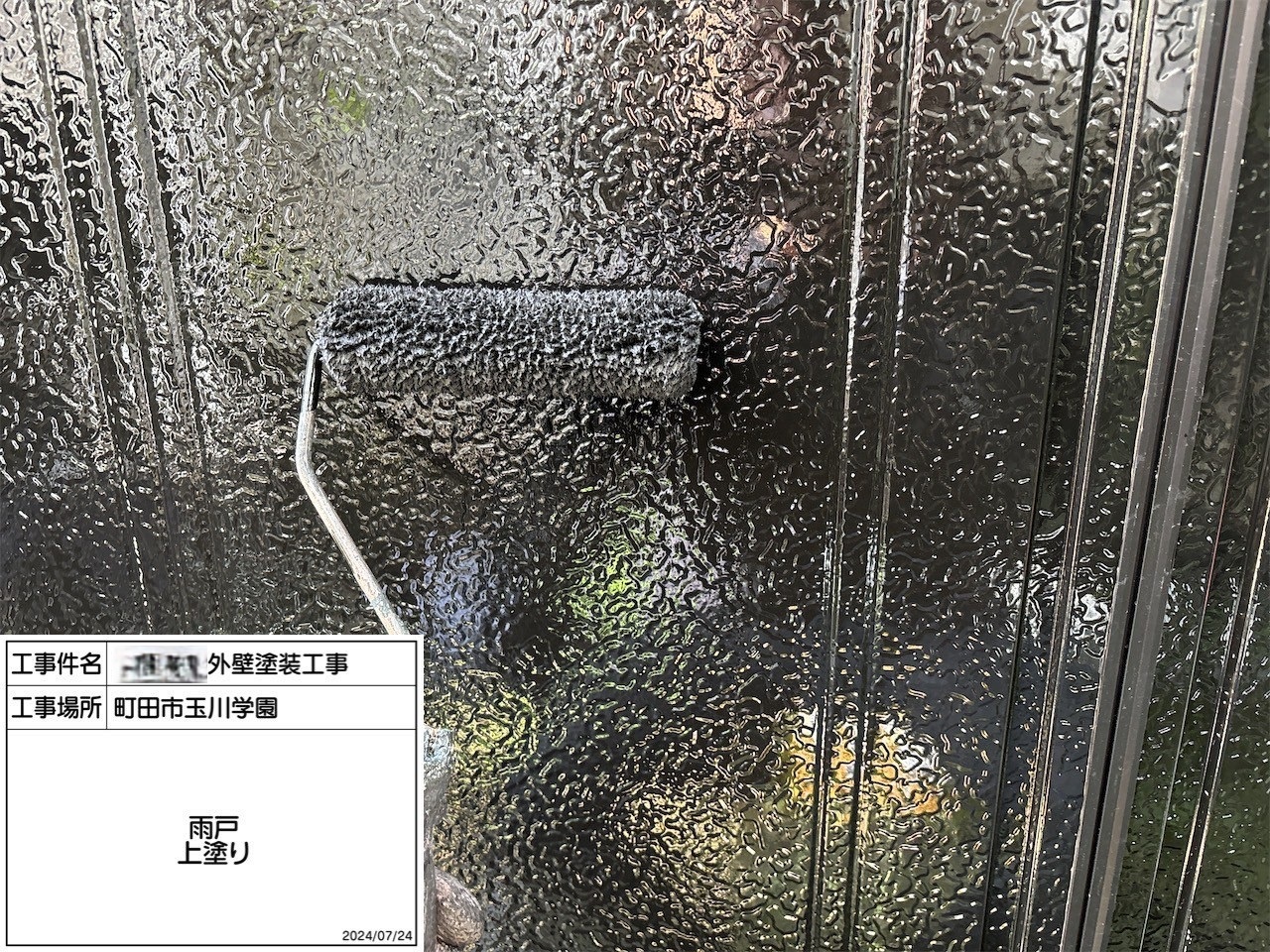
✨仕上げの工程です
中塗りが完全に乾燥した後上塗りを施します
上塗りは美観を整え耐久性を高める
最後の仕上げの塗装です
中塗りと合わせて2回塗ることで
塗膜が厚くなり紫外線や雨風に対する
耐久性が格段に上がります
特に町田市の環境を考慮し
選定した塗料でしっかりと保護します
これで美しい光沢のある雨戸へと生まれ変わります
6️⃣ 完了
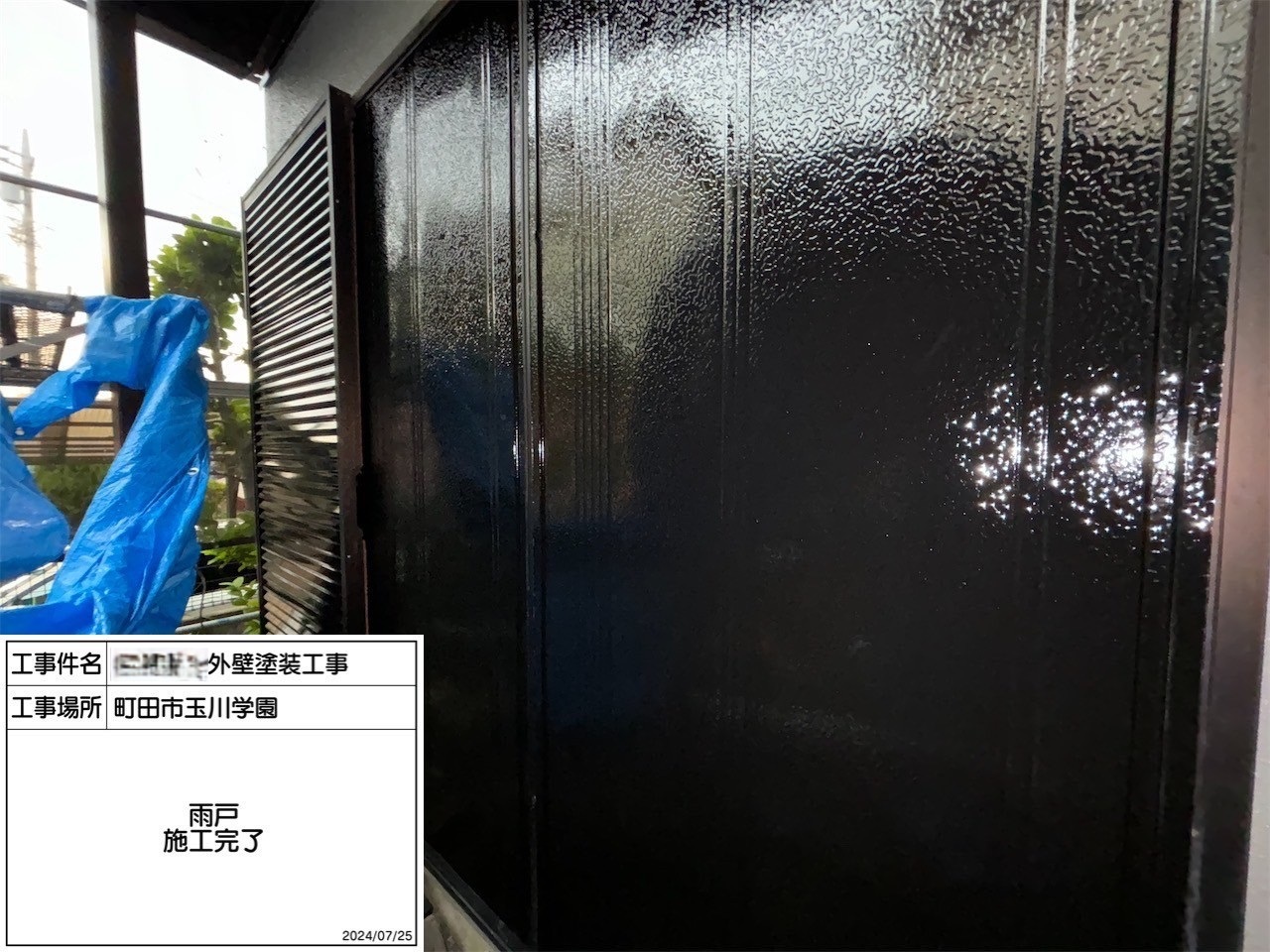
🌟全ての工程が終了し完成です
施工前の色褪せた状態から
艶やかな黒色に生まれ変わりました
これで雨戸はしっかりと保護され
今後数年間は安心してお使いいただけます
お客様にも仕上がりをご確認いただき工事完了となります
====================
まとめ
🔑雨戸塗装は家の寿命を守る鍵です
今回は町田市玉川学園での
雨戸塗装工事の事例をご紹介しました
雨戸の塗装で最も重要なのは
写真でお見せしたケレンという下地処理です
適切なケレンを行い、その後の工程を
確かな技術で施工することで雨戸の耐久性は大きく向上します
町田市で雨戸の色褪せやサビにお悩みの方は
ぜひ一度専門業者にご相談ください
地域に根ざした私たちがお力になります
📞町田市でのリフォームに関するご相談はお気軽にどうぞ






































